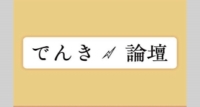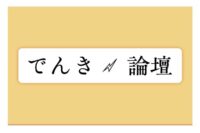▼旧一電A社=発電コスト(規制料金の発電費相当分)15円/キロワット時▼旧一電B社=同20円/キロワット時▼新電力C社=自社電源を持たない――を仮定する。
A社発電部門が供給力全量を卸公募に供出し、約定価格が17円/キロワット時となった。A社小売部門もこれを購入するが、C社も相当量を落札・購入し、B社エリアに進出する。その結果、A社小売部門は供給力が不足し、B社で余剰となった供給力(20円/キロワット時)を調達する。
この時、A社小売部門は同社発電部門の電気を17円で買って規制料金である15円で売るので、1キロワット時あたり2円の逆ザヤとなる一方、発電部門はコスト15円の電気を17円で売ることで2円の追加利益を得るので、小売部門の逆ザヤは穴埋めされる。つまり社内取引をしている分には監視等委の言うとおり、適正な費用回収ができる。しかしB社の余剰電力を購入する逆ザヤは5円となるので、発電部門の追加利益ではカバーし切れず、A社の収支は悪化する。
つまり、A社が社外から卸電力を調達する場合は、その価格の不確実性から適正な費用回収ができないリスクがあり、四国電力がこれを回避しようとするのは合理的であると筆者は思料する。
このように容易に反証できる判断をなぜ監視等委が行ったかは謎である。ひとつ考えられるのは、監視等委が一物一価の市場を想定していたことだが、これは現実の電力市場では想定しがたい。思うに、監視等委は経済学の教科書の理屈を単純に信奉しすぎていないか。これは限界費用玉出しにも通じる。すなわち、完全競争市場では限界費用玉出しも内外無差別も利益を最大化する合理的な行動であるから、「旧一電等に邪(よこしま)な意図がないなら、規制されなくても自主的にこれらの行動をとるはずだ」といった理屈で、自主的な行動を強いてきたとは言えないか。
実際、監視等委が再エネTF会合に提示した資料には「依然として、大手電力会社においては、取引所や新電力などの社外に卸売を行えばより高く売れる状況であっても、こうした比較・判断をせず、当然のように自社小売から需要家への販売を優先しており、場合によっては利益を伴わない販売価格で需要家に販売することで、シェアを拡大しようとする行動パターンに陥りがちであった」との記述がある。
内外無差別を通じて、シェアの維持・拡大を優先する薄利多売戦略に陥りがちであった旧一電等に対し、社内外問わず、高く売れる相手に売る、より合理的な行動を促したといった意識も伺える。内外無差別が善意に基づく指導だとしても、古い競争モデルに基づくものであり、電力需給不安をもたらす懸念があることは冒頭で指摘した通りだ。現実の電力市場、電力システムはそれほど単純なものでないということだ。
電気新聞2025年1月20日
>>電子版を1カ月無料でお試し!! 試読キャンペーンはこちらから