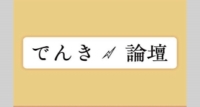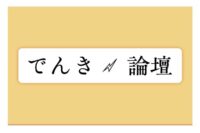監視等委が行った最新の評価によれば、評価対象の10エリアのうち6エリアで、内外無差別が担保されているとのことである。経過措置、すなわち低圧需要家保護のためとして供給義務・規制料金が残された状況の下で内外無差別が担保されるならば、供給義務が課されている旧一電等とクリームスキミングが自由にできる新電力が競争することになる。これでは新電力が有利なのは明らかである。寡占状態にある発電市場のゆがみを解消する目的で行った内外無差別が、経過措置料金を残していることによって新たなゆがみを生んでいるわけである。
経過措置であるので、いずれは解除される。解除の条件は次の3点とされている。
(1)電力自由化の認知度やスイッチング(小売電気事業者の切り替え)の動向など、消費者の状況
(2)シェア5%以上の有力で独立した競争者が区域内に2者以上存在するかなど、競争圧力
(3)電力調達の条件が大手電力小売部門と新電力との間で公平かなど、競争的環境の持続性
現時点では、(2)の条件(シェア5%以上の有力で独立した競争者が区域内に2者以上存在)が満たされていないことなどを理由に、経過措置は解除されていない。法的独占の保証がなくなったにも関わらず、供給義務・料金規制が残されるのは本来不合理である。これが8年以上も続いていること自体が異常なことだが、それ以上に、この状態が続くことは監視等委が旧一電等に内外無差別を求めた理屈が破綻することを意味する。
監視等委は旧一電等に内外無差別を求めるにあたり、強制力を持った制度ではなく、事業者に対し自主的なコミットメントを要請するというアプローチを採った。この理由として、一つは独禁法に直ちに内外無差別を義務付ける規定がない、すなわち強制的な措置を採る根拠がないことがある。さらには、内外無差別は利益を最大化する行動であって、強制されなくても要請を受けることが旧一電等にとって合理的な行動であるはずということがある。
しかるに、「経過措置を残したままの内外無差別」を受け入れることは旧一電等にとって明確な不利益であり、これでは法令上根拠のない内外無差別を自主的にコミットした判断が正当化できない。監視等委は、内外無差別が担保されていれば、前述の条件(3)を満たしていると認めるとしているが、それだけでは(2)の条件のハードルが高く、経過措置はさらに長期化するだろう。内外無差別が担保されているならば、経過措置は直ちに解除されるべきだ。もともと上記の(1)~(3)の条件は、内外無差別の取り組み以前に作られたものだ。状況が変わったのだから、監視等委の英断を求めたい。