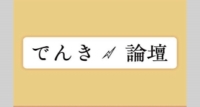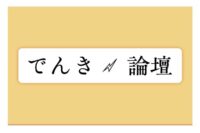◆古いモデル 深追いに疑問
内外無差別な電力卸売の実現は電力・ガス取引監視等委員会(以下「監視等委」)がここ数年重点的に進めている政策の一つである。その目的は「旧一電等(旧一般電気事業者およびJERA)が発電設備の大宗を保有している中で、小売電気事業者間で電源アクセスのイコール・フッティングを確保し、小売市場における競争を持続的に確保するため」とされる。
他方、「電源投資のインセンティブをそぐ」「燃料調達の不確実性とリスクを高める」、ひいては「電気の安定供給に悪影響が及ぶ懸念がある」との指摘が各種審議会でなされている。発電部門は参入自由な市場だが、建設・運転・燃料調達などのプロセスは相応のリスクを伴う。これらのリスクを十分に反映した価格や契約条件が実現する見通しがなければ、新たな投資に踏み切るよりも、内外無差別これ幸いと「他人のふんどしで相撲をとる」ことを選択しがちになると容易に想像できる。これは旧一般電気事業者であれ、新電力であれ、同様であろう。
筆者は本論壇の第1回で、「卸電力市場の価格シグナルによる電源投資の最適化を期待する」従来の電力システム改革モデルを古い競争モデルと呼んだ。電力需要の伸びが緩やかで、地域独占時代の貯金を食いつぶせば安定供給が維持できた時代が終わり、世界中の電気事業が何十年かぶりに大規模投資が必要な時期に入ったところで、古い競争モデルは限界が顕在化している。
そして、古い競争モデルの対案としてハイブリッド市場という概念を紹介した。そこでは、本論壇第4回で市村拓斗氏が言及した『電源版マスタープラン』により必要な投資量が定められる。投資の主体はオークション等を通じて選定され、選定された投資は送配電部門と同様に全ての小売事業者によって支えられる。ここでは発電分野は発送電分野と同様の協調領域となるので、小売事業者への卸売は、実は内外無差別とするのが自然である。
しかし今の内外無差別は、既に限界が顕在化している古い競争モデルを非対称規制によりテコ入れしようとするもの、新規参入者に権利を与えるだけのものである点で、ハイブリッド市場のそれとは似て非なるものだ。特に、内閣府の再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(以下「再エネTF」、現在は廃止)による介入以降、監視等委による監視がいたずらに先鋭化しており、この取り組みを深追いしても資源と時間の浪費にしかならないと筆者には思える。
もっとも、古い競争モデルからの脱却は一朝一夕にはできない。このため、今のモデルを当面是としたとしても今の内外無差別が経過措置を残していることにより市場をゆがめている問題がある。
>>電子版を1カ月無料でお試し!! 試読キャンペーンはこちらから