<<前回へ
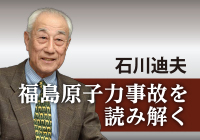
電気新聞の「時評・ウエーブ」欄に寄稿した福島原子力事故についての論評から21編が、今年5月から毎週木曜日に電気新聞ウェブサイトのスペシャルコーナーに連載された。拙著『考証 福島原子力事故 炉心溶融・水素爆発はどう起こったか』からの概要紹介を中心に、福島原子力事故から学ぶべきことを論じてきた。新聞掲載時点より考察が深まった部分は加筆、修正している。
ウェブ連載も今回で終了となるので、全体のまとめを書いておきたい。詳細は拙著に譲るが、本連載で述べたかったのは以下に述べる3点だ。いずれも、これまでの原子力安全の常識を覆し、原子力安全を強化する学説である。
この最終回は少し長くなるので覚悟してほしい。拙著を読んでいない方にとっては、にわかに信じられない話かもしれないが、この内容に賛同してくれる人がいれば、ぜひ力を貸してほしい。では始めよう。
学説1 炉心溶融は化学反応で起きる。故に防ぐことができる

炉心溶融はどうやって起きるのか――。従来の学説では原子炉から出る崩壊熱によって炉心は溶融する、としていた。しかし東京電力の福島原子力事故データを一つ一つ丹念に読み解くと、これは疑わしい。拙著では、事故で高温となった燃料棒の被覆管(ジルカロイ)と冷水が反応し、大量の熱が短時間に発生したことで起きたと考えれば、東京電力が残した事故データと矛盾することなく、事故経緯が説明できることを論証している。
世界を驚愕させた炉心溶融直後の水素爆発は、ジルカロイと水の反応で還元された水素が原因である。炉心溶融と水素爆発が同じ原因(化学反応)に帰することは、福島第一原子力発電所の1~3号機で溶融・爆発(2号機は水素爆発に至っていない。その理由は拙著参照)が共通して起きていることからも明らかである。これは、事故データを丹念に分析すると自ずと分かることであり、この論証に沿って考えれば、40年前に起きた米国スリーマイル島(TMI)原子力発電所の溶融・爆発もまた同じ経緯(化学反応)をたどったことが分かる。
大切なことは、炉心溶融(と、それに続く水素爆発)が化学反応で起きた事実である。化学反応であるから、反応条件が成立しなければ――冷水と高温被覆管(ジルカロイ材料)が共存しなければ――、反応(炉心溶融)は起きない。炉心溶融は防止できるのである。崩壊熱は物理的現象であり、なくすことは難しいが、化学反応は防止することが可能だ。
防止する方法はいくつかあるが、故・吉田昌郎福島第一原子力発電所長が試みた炉心減圧もその一つだ。減圧による蒸気の放出で炉心は冷え、燃料棒温度は飽和温度(約200℃程度)にまで下がる。この低い温度では被覆管は冷水と反応できないから、減圧で炉心が冷えたチャンスを逃がさず冷水を注入していれば、炉心溶融は起きなかった。残念なことに、冷水の注入は2時間ほど遅れた。この遅れで燃料棒温度は再上昇し、炉心は溶融に至った。


















