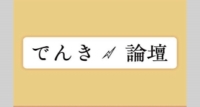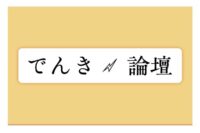電力市場に潜む「燃料危機」の根本的な問題は何であろうか。ここでは、二つの問題を指摘したい。
第一に、「市場シグナルの欠如」が「限られた燃料資源」の最適配分を妨げていることである。過去の「燃料危機」においては、必ずしもすべての発電所で同様に在庫が減った訳ではない。例えば、今年3月の「危機」では、全国の発電用LNGの在庫が3月末に前月比28%下がったのに対し、石炭は5%増えている。この時はLNGの価格が急速に下がり、石炭より安価になったため、消費が石炭からLNGにシフトしたのだ。
LNGの在庫減少が想定以上に早い時には、予防的に入札価格を上げて市場での落札量の調整を図るのが、本来、事業者にとって経済合理的な判断ではないだろうか。「限界費用入札」を継続し、燃料制約で供給力を喪失することの代償(=機会費用)が極めて大きいからである。
適切なシグナルは市場全体にも恩恵をもたらす。燃料に余裕のある発電所の稼働が増えたり、早期のスポット調達やデマンドレスポンスが促されたりして、最悪の事態を回避すべく資源の配分が行われるはずである。残念ながら、現在の市場では発電所停止という事態を迎えるまで、「危機」は静かに潜航するのである。
第二に「量の予備力」(燃料や貯水などエネルギーの備蓄)の低下である。端的にいうと、これまで燃料の備蓄の多くを担ってきた石油火力の退出である。石油火力は消費の1カ月分程度のタンク容量を持っていたが、その背後には、輸入者として国内に70日の備蓄義務を持つ石油元売りや商社が供給元として控え、その大量の在庫を、内航船やパイプラインを通じて調達できていた。その石油火力の設備は16年度の電力小売全面自由化以降、約2200万キロワットも減少しているのである。
石油火力の代わりに主力になったLNGおよび石炭火力だが、それぞれ、ミドル、ベース火力として計画的な運用が前提であったため、在庫能力はLNGで2~3週間分、石炭で4週間程度と最小限である。石炭の4週間というのも、大雨による生産停止や港の船混みなどで、出荷が遅れることも多い燃料ということを考えると、額面通りには期待できない。
なお、石油火力のような予備力は、市場におけるコール・オプション(商品を買う権利)と同様、市場の価格変動(ボラティリティ)で価値が評価されるものだ。従って、「限界費用入札」による市場のボラティリティの抑制は「量の予備力」の退出も促してきたはずである。
>>電子版を1カ月無料でお試し!! 試読キャンペーンはこちらから