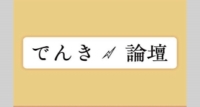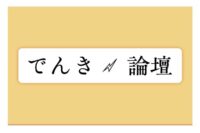◇限界費用入札 シグナル発せず/「量の予備力」維持不可欠
猛暑が続き、今夏も「電力危機」が話題になったが、実は「燃料危機」も迫っていた。8月中旬、8月末に2~3日ずつ、多くの発電所が燃料制約のため停止や出力低下を余儀なくされ、おのおの5千~6千キロワットの供給力が失われた。台風の接近で燃料の荷揚げができないのが要因とのことだが、せいぜい3~4日、燃料の受け入れが滞ると発電を継続できないほど、在庫が下がっていたということだ。
実は、今年は3月末にも同様の事態が発生しており、一年に3回も危機が訪れている。幸い8月の危機は土日と重なり、3月末は需要期の終わりであったことから、電力価格も極端に高騰することなく終わったが、これが需要期の平日と重なっていたら、2021年1月のような電力市場の大混乱を招いていた可能性もある。
それでは、繰り返される「燃料危機」の舞台裏はどうなっているのか。
発電用燃料は、おおむね消費の2カ月前までが調達期限である。この「燃料ゲートクローズ」後に電力市場に投入可能なのは、手当て済みの燃料2カ月分に在庫を加えた「限られた燃料資源」なのである。これが、発電所がガスのパイプラインや炭鉱に近接し、常に発電に必要なだけ燃料を使える国とは違う、「資源なき国」の電力市場の現実である。
その「限られた燃料」の消費が、年々読みづらくなっている。卸電力取引所の発展とともに、旧一般電気事業者(以下、旧一電)の供給エリアのみならず、全国各地の発電所や電力系統の状況に影響を受けるようになった。さらには急増する太陽光の発電量の変動や、近年発生するようになった石炭とLNGの価格の逆転などによって、発電所の稼働は予想外に増減するようになったのだ。
>>電子版を1カ月無料でお試し!! 試読キャンペーンはこちらから