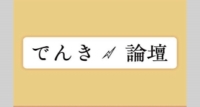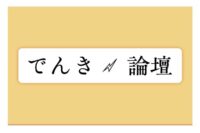電気事業や電力システムをめぐる社会科学分野(経済学・経営学・経済法・会計学)の研究は、20世紀初頭からの電気料金設定にかかわる研究(ラムゼイ料金、ホテリングなどによる二部料金制度の研究)から始まり、1983年にジョスコウ・シュマーレンシーの「電力の市場」が著されて以降は、より良い自由化・電力市場の姿がテーマとなった。自由化実践初期の英国で制度設計にかかわったリトルチャイルドをはじめ、産業組織論を中心とした経済学、さらには独占と競争を扱う経済法分野の研究者もより良い電力市場・規制の姿を求めて研究や議論を重ねてきた。
ここで注意すべきなのは、これらの探求や洞察がすべて1920年代に本格的に始まった伝統的電気事業を前提としたものである点である。伝統的電気事業では、電気の生産能力はすべて水力・火力・原子力などの回転発電機にあり、送電や配電ネットワークは発生した電気をユーザーに一方向に送り、すべての発電機を指令どおり動かし(ディスパッチ)信頼度維持を行うために存在し、ユーザーは電気を使うだけの存在である。
ここでは電気の対価(料金)や競争導入に伴って登場する市場の設計、場合によって支配的事業者の対処問題などが検討対象であり、特に市場メカニズム(価格シグナル)によって、電源は適切に更新・補強されるのかが最大の論点となった。そして現在のところ、それに対する答えは否定的であり、「市場メカニズム的なもの」と「そうでないもの」のミックスしか解決策はないというのが一定のコンセンサスとなっており、かなりの自由化地域ではその前提で幅広い負担による電源投資誘導が行われている。
>>電子版を1カ月無料でお試し!! 試読キャンペーンはこちらから