<<前回へ
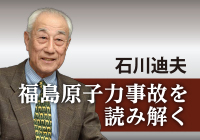
電気新聞2015年12月14日掲載のコラムを加筆・修正しています
「炉心から水がなくなると炉心溶融が始まる」。これまで原子力関係者が言い続けてきた、また誰も疑問を抱かなかったこの原子力常識に、福島事故が疑問符をつけた。これが今回のテーマだ。
事故例を調べてみると、溶融時点での炉心水位は事故によってそれぞれ違っている。TMI事故<編注:米スリーマイル島原子力発電所事故>では、冷却水が炉心の半ばくらいまで残っている状態で、炉心は溶融した。初めての炉心溶融事故だったから、誰もこの結果に疑問を抱かなかった。
福島事故の場合、2号機の溶融は、炉心から完全に水がなくなった後(炉心下約1mの水位)で起きた。3号機は両者の中間で、溶融時点の水位は炉心の最低位置付近であった。ご覧のように、炉心溶融と水位の間には明確な相関がない。冒頭の原子力常識とはいささか違っている。

より完全に常識を疑わせる事例が、長時間の空焚き状態の後爆発した1号機の知見だ。
1号機の炉心から冷却水がなくなったのが3月11日午後8時頃。炉心溶融によって派生する水素爆発が起きたのは、何と半日以上も経った翌12日の午後3時36分だ。前報で述べた様に、高温のジルカロイ<編注:ジルコニウム合金のこと>が水と反応しない限り、大爆発を起こす水素ガスは発生しないことを思い出して欲しい。
ちなみに、水が完全に蒸発して圧力容器が空っぽになったのが11日午後11時という深夜だ。炉心から水がなくなってから爆発までの約20時間、一体全体、原子炉に何が起きていたのか。データがないから分からないが、炉心から水がなくなると溶融するという原子力常識と1号機の事故データが、全く相違していることだけは明白だ。
「炉心から水がなくなると炉心溶融が始まる」という常識の出発点は、水がなくなった炉心は崩壊熱を除去できないから、温度上昇を続けて遂には溶融に至るという、至極単純な仮定を拠り所とする説に発している。この仮説は断熱仮定と呼ばれ、炉心からの放熱を全く無視するという仮定を用いる。物事の目安を付けるために行う粗い計算方法で、これに従えば、炉心溶融は事故発生後、数時間の後に始まる。
断熱仮定の欠点は根幹をなす仮定そのものにある。2000℃を超える高温の溶融炉心が出す大きな輻射熱を、断熱仮定ではゼロにするのであるから、推論に現実味はない。このような間違いを犯すのは、常温下で暮らす我々は高温世界の体験がないからである。
複雑な形状を持つ炉心の輻射熱を正確に計算することは難しい。だが、精度を度外視した検討を付けるための粗い計算では、炉心の発熱(崩壊熱)と放熱(輻射熱)は2000℃近辺で均衡する。何事もなければ、水のない炉心はこの程度の温度状態で、圧力容器の中で均衡を保つと推察できる。
だが好事魔多し。世の中には邪魔者がいて、上記の均衡は長時間持続しないのだ。実は、地球の重力が悪戯(いたずら)をする。2000℃の高温ともなると燃料材料は少し柔らかくなり、重力の作用で高温部分が垂れ下って、徐々に接近集合して炉心下部支持盤に集まり、これを熱で溶かして穴を開ける。その後、高温の燃料材料は、搗(つ)きたてのお餅が手からゆっくりと脱落するように、支持盤から分離脱落して圧力容器の底に堆積し始める。
ところが、受け皿の圧力容器の底自体も、輻射熱によって600~700℃に加熱されているから、鉄としての強度を失っている。ポトンポトンと落ちて堆積する燃料材料の重量に耐えかねて、ある時間の後には圧力容器の底が抜ける。燃料材料はさらに落ちて、格納容器の床上に堆積する。この状況は、海水注水が始まった12日午前4時頃には、既に起きていたと推測される。
断っておくが、この貫通落下はテレビで放映されたCG動画のように、炉心が液体と化して流れて落ちたものではない。あくまでも固体状態での落下で、ポトン、ポトンである。温度の低い格納容器の床上に集積して、冷えて築山を築いたと考えている。
チェルノブイリ事故<編注:旧ソ連のチェルノブイリ原子力発電所事故>での知見では、築山の外側は冷えて壁となり、その内側は落下してくる燃料材料の溶融池ができたという。燃料材料自体が持つ崩壊熱で互いに暖め合って溶融して池を作り、3度にわたって外壁を溶かして、池内の溶液は流出したという。
1号機の溶融は、チェルノブイリとは少し様相が異なる。海水の注入によって格納容器の床上に溜まった海水が増して、築山を乗り越えて内部の池に流入し、池の中にある高温の燃料材料(ジルコニウム)と反応したと思われる。ベント開放で格納容器圧力が低下し、消防ポンプの吐出量が活発となった直後の午後3時半に、爆発が起きているのがその証拠だ。チェルノブイリとは違って、燃料材料は崩壊熱で溶融池を作る程の、時間的余裕がなかったためであろう。
注水の増加で高温ジルカロイと水の反応が激しくなり、その発熱で燃料材料が溶融し、同時に水素ガスが大量発生して爆発が起きた。その詳細は、拙著『考証 福島原子力事故』をご覧頂きたい。
1号機の事例は、「炉心から水がなくなると溶融が始まる」という原子力常識は間違いであると共に、「原子炉から水がなくなっても、炉心は簡単には溶融しない」ことを教えている。
電気新聞2015年12月14日
※『考証 福島原子力事故 炉心溶融・水素爆発はどう起こったか』に、この内容が詳しく書かれています。
次回へ>>
東京電力・福島第一原子力発電所事故から7年。石川迪夫氏が2014年3月に上梓した『考証 福島原子力事故ー炉心溶融・水素爆発はどう起こったか』は、福島原子力事故のメカニズムを初めて明らかにした書として、多くの専門家から支持を得ました。石川氏は同書に加え、電気新聞コラム欄「ウエーブ・時評」で、事故直後から現在まで、福島原子力事故を鋭い視点で考証しています。このたび増補改訂版出版を記念し、「ウエーブ・時評」のコラムから、事故原因究明に関する考察を厳選し、順次掲載していきます。


















