<<前回へ
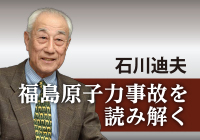
電気新聞2015年8月31日掲載のコラムを加筆・修正しています
僕は若い頃米国への留学で、SPERT(Special Power Excurtion Test)実験という名の事故時の燃料棒挙動の実験に参加させて貰った。留学先がそのメッカだったのが縁で、それ以降20年間ほど、米独日の3カ国が協力して実施した軽水炉の安全研究の一端を担った。余談だが、この3カ国協力の実験成果が、今日の国際原子力機関(IAEA)の国際安全設計基準の基となっている。
さて、その過程での実験で、僕は二酸化ウラン(UO2)の燃料棒が溶融して流下する現象に出合ったことが一度もない。燃料棒は過熱された高温状態では直立姿勢を保ったままであるし、実験後には冷えた分断片となってバラバラに出て来る。燃料棒が溶融し液化した痕跡は、ペレットの中では認定できるものの、被覆管を含めた燃料棒全体が溶融する状況は、実験で見られたことはない。
燃料棒が高温状態でも直立姿勢を保って溶融しない理由は省略する。酸化膜の融点は約2700度と高い。燃料棒の芯をなすUO2ペレットの融点2800度と、ほぼ同じ程度の高温だ。このような融点の高い物質を、坩堝(るつぼ)なしで溶融させる事は実際上不可能と考えれば、理解し易いであろう。
だが一般には、水を失った炉心は崩壊熱で加熱されて溶融し、発熱の高い中心部分から溶けると信じられている。福島事故後にテレビで度々放映された動画は、溶融した炉心が原子炉の内部を流れて下に落ち、格納容器の床を融かしていく。だがこれはSFもどきの想像動画で、現実には起き得ない。

そのように言う理由は、高温物体が放射する輻射熱が非常に大きいからである。坩堝の中であれば話は別だが、融点の高い物質は溶融して流動し始めた途端に表面から固化が始まる。融点の高い物質は、過熱され続けない限り、熱が輻射で外に逃げ出すので溶融状態を続けられない。我々が暮らす生活環境は精々1000度以内。3000度の超高温の世界など経験できない。だから、誰もよく知らないし、つい忘れてしまう。高温の物質が出す輻射熱もその一つだ。
輻射熱は、ステファン・ボルツマンの法則に従って、物体の表面温度(絶対温度)の4乗の大きさで放散される。その代表が太陽光で、表面温度6000度から放射される輻射熱が、宇宙空間1億5000万kmを旅して地球に届き、我々を暖めてくれる。
輻射熱の大きさを知るために、我々が経験できる表面温度1000度と、思考上の融点3000度の溶融炉心が出す輻射熱を比較して見よう。表面温度の差は僅(わず)か3倍だが、輻射熱量はその4乗比だから、大きさは81倍にもなる。高温物質が出す輻射熱はこれほど大きい。
融点の高い物質は、少量ならレーザー光線の照射で溶かせる。だが照射を止めると、温度は瞬時にして数百度に急降下するという。輻射熱の放散で直ちに冷えるからだ。溶融炉心のような高温の物質が液化流動するなどという話は、輻射熱の小さい常温世界に住む我々の、妄想の産物なのだ。
しかし、現実に福島には溶融した炉心が存在する。TMI<編注:米・スリーマイル島原子力発電所>事故でも炉心溶融は起きた。この溶融を誘起した熱は、前報で述べた様に、冷水注入により折損、分断した燃料棒の、高温ジルカロイ<編注:ジルコニウム合金のこと>と水の間の激しい化学反応熱であった。この熱によって反応が起きた周辺の燃料棒が溶けて移動し、ある程度互いに溶着、合体する。この溶着合体は、反応が起きたごく短い時間の話である。これが最初の炉心溶融(燃料棒溶融)ある。
ここで前記の、燃料棒実験の知識が生きてくる。高温では直立していた燃料棒は、水で急冷されて、バラバラに分断される。その分断面には、当然のことながら高温のジルカロイが露出するから、水と接触して激しい反応を起こす。この反応熱は非常に大きいため、分断面周辺の燃料が溶けて合体する。これが最初の炉心溶融の説明だ。
反応は激しいので、短時間で終わる。反応が終われば、発熱はなくなるから、溶融、合体した燃料(最初の溶融炉心)の表面は急速に冷えて固まる。溶融物の下に水があれば尚更だ。TMIの溶融炉心が場所を変えず、元の炉心位置に残っていたるのはこの故だ。
僕は、反応熱で溶けた最初の溶融炉心は、ある程度合体して、第2の溶融炉心を受ける鍋のような物の原型を作るか、もしくはTMIの場合はある程度の大きさの炉心を包む不完全な風袋(坩堝)と化して、その中で発生する崩壊熱が時間を掛けて(坩堝の中の)燃料物質を溶かして、均一な合金(第2の溶融炉心)を作ったと推測している。
このように考えれば、TMIに出来た溶融炉心(卵の殻とその中にある均質な合金)の説明が、事故現象と矛盾することなく説明できる。また福島の事故での炉心溶融経緯も、公表されたデータに沿った説明が可能となる。
ところで、化学反応熱と崩壊熱の相違について一言。化学反応熱は、反応が起きた場所での発熱だから、その近傍だけを集中して強烈に加熱する。発熱時間も短い。逆に崩壊熱は、核分裂した放射能が出す熱だから総量は大きいが、炉心全体に広く薄く発生する、長時間の発熱だ。この両者は発熱の状況が全く違う。この相違が、事故時の炉心挙動に及ぼす影響は大きく、事故現象を複雑にさせる。よく注意する必要がある。
以上、本日の福島事故が教える新常識は、燃料棒は冷水の注入により折損、分断するが、崩壊熱で溶融はしない、である。
炉心は燃料棒が折損して崩壊する。崩壊した後、炉心は化学反応熱に溶融するが、輻射熱が大きいので早期に固化して、第2の合金状の溶融炉心を作るための坩堝を形成する。炉心が溶けて流動する事は、輻射熱の大きさを考えれば、あり得ない。
電気新聞2015年8月31日
※『考証 福島原子力事故 炉心溶融・水素爆発はどう起こったか』の増補改訂版に、この内容が詳しく書かれています。
次回へ>>
東京電力・福島第一原子力発電所事故から7年。石川迪夫氏が2014年3月に上梓した『考証 福島原子力事故ー炉心溶融・水素爆発はどう起こったか』は、福島原子力事故のメカニズムを初めて明らかにした書として、多くの専門家から支持を得ました。石川氏は同書に加え、電気新聞コラム欄「ウエーブ・時評」で、事故直後から現在まで、福島原子力事故を鋭い視点で考証しています。このたび増補改訂版出版を記念し、「ウエーブ・時評」のコラムから、事故原因究明に関する考察を厳選し、順次掲載していきます。

















