<<前回へ
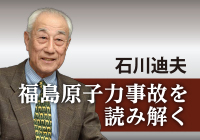
2014年8月20日に電気新聞に掲載したコラムを再掲しています
今回も、拙著『考証 福島原子力事故』からの抜粋紹介だ。
金属ナトリウムを水の中に放り込むと爆発する。空気にさらすと表面に酸化被膜が出来る。ナトリウムは化学的に不安定だから、常温でも酸素と反応するからだ。
ナトリウムほど激しくはないが、一般金属類も高温では不安定になり、水と反応する。燃料被覆管のジルカロイ<編注:ジルコニウム合金のこと>も同じで、温度1300度以上では反応は止まらない。この反応の結果できた水素が、福島事故での爆発原因だ。
ちなみに、安全審査における冷却材喪失事故の判定基準が、被覆管表面温度1200度以下と定められているのは、この故だ。
通常運転状態での被覆管温度は、冷却水温を少し超える300度前後であるから、反応の心配はない。冷却が不足したり、福島事故のように炉心から水がなくなると、燃料棒温度は上昇する。

被覆管温度が800度程になると、管表面は水と反応して薄い酸化被膜を作る。この被膜は、非常に強靱で緻密だ。一旦被膜が出来ると水を通さない。この結果、管の内側にあるジルカロイは水と接触できないので、更に温度が上昇しても酸化反応は進まない。
例えれば、天の川に隔てられた織女と牽牛のように、酸化被膜に邪魔されて、高温のジルカロイは水と出合えず反応できないのだ。
説明は省くが、さらに高温になると、管内面にも酸化膜ができる。こうなると被覆管本体は、酸化ジルコニウムの被膜によって内外両面が挟まれて、サンドイッチ状になる。厄介なことに、この酸化被膜の融点は約2700度で、本体のジルコニウム(融点約1800度)より大幅に高い。このため奇妙なことが被覆管に起きる。
今仮に被覆管温度が2000度になったとしよう。酸化被膜には変化はないが、挟まれたジルコニウムは熔けて流れ落ちて、所々に溜まりを作る。このため燃料棒の形は崩れて凹凸した形状になる。
この状態で被膜が破れると、溜まりの高温ジルコニウムが水と出合って激しく反応し、大量の水素が発生して爆発原因となる。逆に、被膜が破れずに冷えれば、ジルコニウムは凝固し反応しないから、爆発は起きない。燃料の冷却状況が爆発を左右するのだ。
この、史上初の大博打が、故吉田所長のとった原子炉の減圧と海水注入だった。安全弁を開いて減圧すれば、吹き出る蒸気で炉心が冷える。同時に、高温のジルコニウムも冷えて固まる。
この冷えた状態から、時刻をおかずに冷たい海水を注入していれば、炉心はさらに冷えて爆発は起きなかった。博打は九分通り成功していたのだ。
だが、実際は海水注入作業が2~3時間遅れた。この間に発生した崩壊熱によって、炉心温度は再上昇し、高温に戻ったジルカロイが海水と出合った。
2、3号機の炉心溶融とそれに続く水素爆発<編注:2号機はブローアウトパネルの落下で水素が建屋から流出したため、水素爆発に至らなかった>は、海水注入の遅れ、中断の結果だ。惜しまれる空白であった。その理由は、減圧による海水注入を急ぐ余り、減圧による炉心温度の低下と、空白による燃料温度の再上昇を、失念していたからであろう。
30年余り昔、安全性研究の盛んな頃は、冷却材喪失事故の対策として、上記の事柄は熟知されていた。配管の破れ目から噴出する水は、その流れで炉心を一旦冷やしてくれる。炉心への緊急注水は、崩壊熱に負けぬよう、手早く行うよう設計するのが使命であった。名将、詰めを誤ったと言うべきか。
逆に運転員諸君は、この事実を噛み締め、自信を持って欲しい。冷却不足で炉心が灼熱状態に陥っても、減圧徐冷の後、間を置かず注水すれば、ジルカロイも冷却凝固し水とは反応出来ないので、溶融、爆発は防ぎ得ると。
軽水炉の持つ安全耐力は、かくも素晴らしい。開発に尽くされた先人の明を再学習すべしと思う。
電気新聞2014年8月20日
次回へ>>
東京電力・福島第一原子力発電所事故から7年。石川迪夫氏が2014年3月に上梓した『考証 福島原子力事故ー炉心溶融・水素爆発はどう起こったか』は、福島原子力事故のメカニズムを初めて明らかにした書として、多くの専門家から支持を得ました。石川氏は同書に加え、電気新聞コラム欄「ウエーブ・時評」で、事故直後から現在まで、福島原子力事故を鋭い視点で考証しています。このたび増補改訂版出版を記念し、「ウエーブ・時評」のコラムから、事故原因究明に関する考察を厳選し、順次掲載していきます。


















