<<前回へ
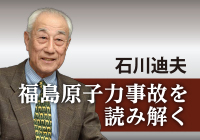
2014年7月8日に電気新聞に掲載したコラムを再掲しています
福島の廃炉議論が、このところ騒がしくなってきた。猫も杓子もマスコミも廃炉評論家なのは、汚染廃液を廻るトラブル報道にあるのか、40年後の廃炉達成に抱く夢なのか。さてその実情は。
福島の現場では、原子炉建屋プールから使用済み燃料を運び出すなど、破壊された施設を気遣いながら、準備作業が始まっている。その努力は真摯だが、何しろ相手は炉心溶融を起こした原子炉だ。普通の廃炉とは汚染量が違う。
夢実現への最大障害は何と言っても溶融炉心だ。ところが、それが何処に、どんな状態で存在するのか、その情報すらまだない。今から、ロボットを駆使して調べるのが精一杯の現状だ。
東電は100%確実なことしか言えない。間違えば世論の袋だたきに遭う。従って、溶融炉心の所在は、可能性のある場所全体を示すしかない。評論家はそれを鵜呑みにする。ここが問題なのだ。
評論家の思考の底には、事故後度々放映されたチャイナシンドロームもどきの創作映像がある。それは、灼熱した溶融炉心が液化して圧力容器を溶かし、格納容器の床コンクリートまでも溶かし、皮一枚残して固化したという映像だった。それが恰(あたか)も現実であるかのように、頭の中にある。
となると、今後作られるロボット類は、チャイナシンドロームの幻影に影響された、非科学的かつ全体的なものとなる。手探り探査だからそれも良いが、焦点を持たぬ開発は大きな無駄を伴う。

だが、溶融炉心は、拙著『考証 福島原子力事故』に書いたように、テレビ映像のごとく溶融液化して流出したものではない。
その証拠に、同様の炉心溶融を起こしたTMI<編注:米スリーマイル島原子力発電所のこと>の炉心は、全てが原子炉内に残っている。その大部分は、母胎にある胎児のように卵の殻で包まれた形で、元の炉心位置に冷却されていた。残りの一部は横に圧されて、炉心側面を囲む鋼板を溶かして落下したが、全てが圧力容器の底で固化していた。このように、炉心溶融の実態は、テレビ映像とは異なるのだ。
大胆な予測と言われそうだが、僕は、2、3号機の溶融炉心は、TMI同様に圧力容器の中に留まっていると見る。<編注:2014年当時のデータに基づく。東京電力の見解とは一部異なる>
その理由は、炉心の溶融状況がTMIと同じで、高温となった被覆管金属ジルカロイと水の反応であること、反応後も冷却水が圧力容器に存在していたことによる。
問題は1号機だ。非常用冷却器の不作動により、原子炉の冷却水は完全に蒸発した。圧力容器に水のない状態が、少なくとも4時間続いた。TMIとは、炉心の溶融状況が違うのだ。
だが計算してみると、この状態でも炉心は溶融温度に達していない。崩壊熱が輻射熱となって放射されるためだ。輻射熱とは、一般の方々には、電熱器のヒータが出す熱と思えば良い。ヒータが溶けないように、炉心燃料も溶融とは縁遠い状態にあった。
ただ、輻射放熱の状態は相当高温であるから、炉心材料の一部が柔らかくなって、分離落下したことは十分考えられる。この落下物が、同じく輻射熱で高温柔軟状態になった圧力容器の底を破り、格納容器床上に落下堆積したことも、容易に想像できる。
余談だが、こう考えると、1号機の溶融爆発が時間的に、素直に説明できるのだ。
この堆積物の内部で、炉心材料は崩壊熱により加熱されて、徐々に溶融液化して床上に流出した。その事例が、チェルノブイリ事故にある。1号機も、類似した状況にあったことであろう。
以上が、溶融炉心の所在についての僕の見解だ。蓋を開けてみないと分からない事柄だが、敢えて大胆に推測を述べるのは、近く実行に移されるであろう探査測定の、計画作成の一助になればとの思いからだ。成功を祈る。
電気新聞2014年7月8日
次回へ>>
東京電力・福島第一原子力発電所事故から7年。石川迪夫氏が2014年3月に上梓した『考証 福島原子力事故ー炉心溶融・水素爆発はどう起こったか』は、福島原子力事故のメカニズムを初めて明らかにした書として、多くの専門家から支持を得ました。石川氏は同書に加え、電気新聞コラム欄「ウエーブ・時評」で、事故直後から現在まで、福島原子力事故を鋭い視点で考証しています。このたび増補改訂版出版を記念し、「ウエーブ・時評」のコラムから、事故原因究明に関する考察を厳選し、順次掲載していきます。


















