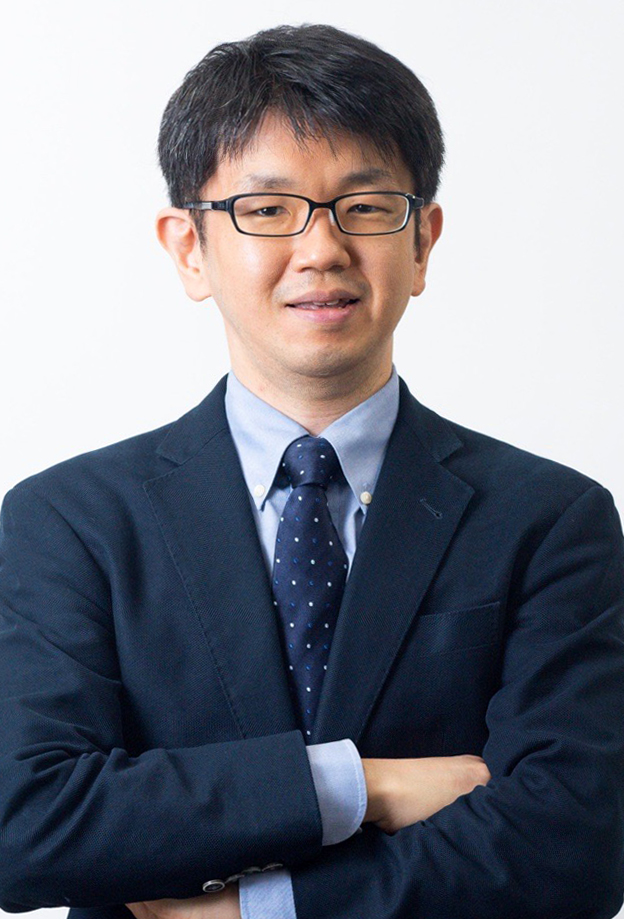
米環境保護庁(EPA)は、大気浄化法に基づき、温室効果ガス(GHG)排出を規制する根拠となっている「危険性認定」の見直しに着手した。気候変動対策に後ろ向きなトランプ政権の狙いは、危険性認定から派生した自動車や火力発電所に対する規制の解体にあると、電力中央研究所の上野貴弘上席研究員は解説する。米自動車産業の保護、化石燃料の増産を掲げるトランプ氏の政策遂行が、気候変動に関する科学的知見に妨げられない政府組織の構築を目指しているとみる。(民直弘)
EPAのリー・ゼルディン長官は12日、危険性認定と、認定から派生した全規制の再検討を発表した。2009年にオバマ政権が二酸化炭素(CO2)などのGHG排出により、現役、将来世代の健康、福祉が脅かされているとして危険性を認定し、この認定から各種の規制が派生したことで、「米経済のほぼ全ての部門を窒息させてきた」と批判。規制緩和でエネルギー価格を引き下げ、家庭の生活費を減らし、自動車産業を活性化させるとした。
オバマ政権とバイデン政権は、法律の条文が曖昧な場合、政府の解釈が合理的であれば従うべきとする米最高裁が確立した「シェブロン原則」にのっとって排出規制を実施してきたが、昨年の最高裁判決はこの原則を覆した。
政府の解釈が法に沿っているかは裁判所が判断することになり、政府の規制権限は大幅に縮小。トランプ政権は新たな最高裁判決に照らして、オバマ政権の危険性認定の合法性を検証し、「1~2年のうちに認定を撤回、または大幅な修正になるのでは」と上野氏は推測する。
ただ、見直し後に待ち構えるのは、環境団体などからの取り消しを求める訴訟だ。最高裁まで争う可能性が高く、判決の行方も「見通せない」と上野氏。トランプ政権の撤回・見直しが最高裁で認められた場合、将来、共和党から政権を奪還した民主党の大統領が排出規制を強化しようとしても、危険性認定からやり直す必要があり、任期の4年で終わらない可能性もあるという。
◆連邦政府、権限縮小に懸念も
別の懸念もある。危険性認定の撤回は、連邦政府が自らに規制権限がないと宣言するようなものであり、各州がこれを名目として独自に規制を開始し、州ごとにばらばらの規制のパッチワークに陥る恐れがある。さらに上野氏は「連邦政府の規制が及ばなくなることで、エネルギー産業や多排出の企業に対し、不法行為を理由として、排出施設の閉鎖を迫る訴訟や気候変動による損害の賠償を求める訴訟が全米各地で起きやすくなるのでは」と懸念する。
EPA長官が、認定の再検討開始に当たって、大統領府の行政管理予算局(OMB)との連携を強調した点にも上野氏は着目する。OMBのラッセル・ボート局長は、トランプ氏再選に向け、保守系シンクタンク「ヘリテージ財団」がまとめた政策提言「プロジェクト2025」を執筆した中心人物の一人だ。
ボート局長はプロジェクト2025で、4年ごとに米国の気候変動の影響を評価する「国家気候評価」を作成する省庁横断の「米国地球変動研究プログラム(USGCRP)」を問題視した。USGCRPが大統領の意思決定や政府機関の規則策定で、「選択肢の範囲を狭める要因となっている」と指摘した。
「USGCRPの再構築」を打ち出したボート局長の意図について、上野氏は「オバマ、バイデン政権のような、気候変動対策を重視した政策決定のあり方にメスを入れ、トランプ氏の政策が気候科学に制約されないように切り離すということ」と説明する。
電気新聞2024年3月21日
















