ENECHANGE(エネチェンジ、東京都千代田区、有田一平社長)グループは日本企業と欧州スタートアップのビジネスマッチングを進めている。情報収集役を担うロンドンの拠点と連携し、国内のスタッフがスポンサー企業のニーズを踏まえきめ細かなサポートを行い、提携までの道のりを支えている。エネチェンジの取り組みを契機として、業種を超えた日本企業の横のつながりも広がってきた。
◇少数精鋭で情報収集
世界のエネルギー事業は自由化、デジタル化、分散化、脱炭素化という4つの変化に直面し、「100年に1度」といわれるような転換期を迎える。変化が進む欧州で活躍するスタートアップの技術・サービスへのアクセスを提供するため、エネチェンジが主催するプログラムが「Japan Energy Challenge(JEC)」だ。
スポンサーとなる日本のエネルギー企業と、厳選した欧州スタートアップとのマッチングイベントを開き、その後の提携協議をエネチェンジグループが一貫してサポートする。単なる「勉強」ではなく「ディール・メーク(交渉成立)」を明確な目標に置く。
そのために欠かせないのが綿密な準備。エネチェンジはロンドンに本社を置き、エネルギーベンチャーとして活躍するSMAPエナジー(CEO=城口洋平・エネチェンジ会長)をグループに抱える。
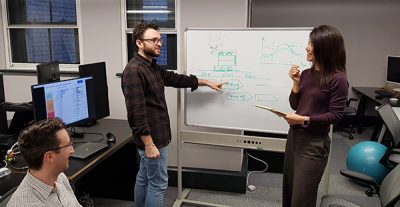
同社の共同創業者であるポール・モンロー・ビジネスマネージャーら3人のスタッフが現地で集めた情報に基づき、スタートアップの「目利き」を行う。19年のマッチングイベントは8月にロンドンで開き、19社のスタートアップを招いた。これに先駆けてモンロー氏が作成した招待企業候補リストは実に600社に及ぶ。
欧州で活躍した実績があることなど、いくつかの条件から候補企業を200社、そこからさらに50社へと絞り込み、経営分析やヒアリングを重ねた。SMAPエナジーでは英国新電力出身者も働いている。欧州の制度、最新動向に精通する強みを生かし、スタートアップの経営者らとフェース・ツー・フェースで情報を集められる精鋭スタッフの存在が、イベントの質を支えている。
◇交渉成立導く徹底サポート
JECのもう一つの特徴は8月のロンドンでのイベント以降も、日本側にいるSMAPエナジーのスタッフがスポンサー企業と欧州スタートアップとの仲介役となって、協業に向けた交渉を支え続ける点だ。

SMAPエナジーの東京オフィスに常駐する鈴木俊也CFOは金融出身で今年夏から同社に参加した。スタートアップの発掘には従来関心があり、多くのイベントを経験したが、誰でも参加できるオープンなものがほとんど。「参加企業を絞り、議論の密度と質を高めるJECは他にない試み。だからこそ具体的な提携にまで踏み込んだ話ができていると思う」と話す。
鈴木さんらはイベント後、ロンドンと連携をとりながら、スポンサーの日本企業、欧州スタートアップの双方と定期的に話し合いを重ね、日本での協業を形にするためのサポートを行っている。
どれだけ優れた技術・サービスを持つ欧州企業でも、言語や制度が違う日本への参入は一筋縄ではいかない。ローカライズが必要な課題を一つ一つ解消し、スポンサーの要望に応じて追加調査も手掛ける。
スタートアップと日本企業の意思決定プロセス、時間軸の違いを認識し、円滑な調整につなげるのも鈴木さんらの役割だ。
日本企業の多くはいったん決めたことを確実に履行する半面、そこに至るプロセスが長く、迅速な意思決定を求めるスタートアップとの温度差が生まれやすい。
それを知るからこそ、鈴木さんは「私たちが『緩衝材』として入ることで、スピードを落とさず、提携交渉を一歩でも前に進めたい」と力を込める。目標はあくまでディール・メーク。そこに向けて全力でフォローアップを続ける。
◇JEC2020/五輪の年、舞台は日本へ
バトンはロンドンから日本へ――。JEC2019のフォローアップと並行する形で、SMAPエナジーは、来年秋に開催予定のJEC2020に向けた準備も着々と進めている。
オリンピック開催地として世界の視線が集まるタイミングを捉え次回は初の日本開催を計画する。
欧州から選び抜いたスタートアップを招き、日本企業とのディール・メークを目指すコンセプトを維持しつつ「SDGs(持続可能な開発目標)」を大枠にエネルギーの周辺領域も含めて広く参加者を募る予定。参加しやすい日本開催となったことで、国内でエネルギー、SDGsに関わる関係者の横のつながりを深める場としても注目を集めそうだ。














