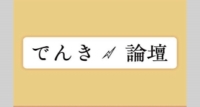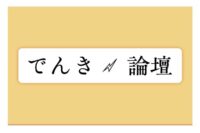EUでは、現在進められている電力市場設計の見直しにおいて、ハイブリッド市場を適用する動きがみられる。ロシア・ウクライナ情勢に端を発したエネルギー危機を受け、消費者を保護する意味でも、脱炭素化のための電源投資を促進する意味でも、従来の市場設計では限界があることを認識した結果である。
新たな制度の一例をあげると、風力、太陽光、地熱、貯水式でない水力、原子力といった今後主力となる脱炭素電源で、各国政府が必要と判断したものは、発電会社と差額調整契約(CfD)を締結し、政府があらかじめ定めた単価による売電収入を事実上保証する。各国政府がこれら電源の必要量を定め、プロジェクトを選定するプロセスがハイブリッド市場のCompetition for the marketに相当する。
EU委員会はこれまで、統一市場の理想の下で古い競争モデルを精力的に追求してきた。いくつかの国では不完全な市場を補うために容量メカニズムが導入されているが、過渡的なものとして渋々認められたもので、卸電力市場の価格シグナルがいつかは機能するようになると信じていたわけである。
しかるに、容量メカニズムは過渡的な制度というスタンスは昨年撤回された。EUのスタンスを引き合いに、日本の容量市場に反対する論調に対峙してきた筆者には、この「手のひら返し」は感慨深いものであった。加えて、今は各国政府が必要な投資の確保に関与していく市場設計の見直しを進めている。ジョスコウ教授らが「これまでの競争モデルはもはや古い」と指摘していたことが認知され、制度設計に生かそうとする動きと筆者の目には映る。
日本でも、足元の電力不足を招いた急進的な改革をカバーし、脱炭素化に向けて必要な投資を後押しすべく、「長期脱炭素電源オークション」が導入される。理論的にはこれはハイブリッド市場に相当すると筆者は考える。また、古い競争モデル、すなわち卸電力市場の価格シグナルに依存して電源投資をする民間資本が現れるとは思えず、政府が枠を設定した長期脱炭素電源オークションが唯一の投資判断のよりどころとなる可能性は大きいと考える。そうなれば、日本もハイブリッド市場に移行したことになる。
>>電子版を1カ月無料でお試し!! 試読キャンペーンはこちらから