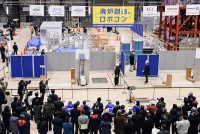背中を押された「前を向いて考えよう」という言葉
今夏、チェルノブイリ原子力発電所(ウクライナ)北側にあるベラルーシを福島の高校生16人が訪問した。現地で様々な研修や多様な交流を実施。その成果を報告する会がこのほど、福島県いわき市で開かれた。研修や交流を通じて自ら感じ取ったことを参加者一人一人がパネル討論形式で披露。現地のゴメリ大学教授からかけられた「前を向いて考えよう」との言葉に背中を押されたとの意見が出たほか、福島の未来に何ができるかに関して「世界の人たちに福島を見てもらい、現状を正しく世界に発信すべき」などの意見が聞かれた。
チェルノブイリ原子力発電所事故から30年に当たる昨夏に、ベラルーシから福島県浜通りの高校生21人が招かれた。このプログラムを運営した福島県広野町のNPO法人ハッピーロードネットの西本由美子理事長は「30年後の地域を担う人材を育てるために非常に意義のある事業」と考えて継続実施を決意。地元企業を中心に寄付を募るなどして今年度も実施にこぎ着けた。
今年は7月24日から8月4日の日程で16人が参加。首都ミンスクでチェルノブイリ事故の移住者の会で体験を聞いたり、ベラルーシ国立大学で意見交換を行ったりした。
発電所に近いゴメリ州なども訪問。ゴメリ大学で畜産学の権威であるビクトル・アベリン教授や学生などから農業・畜産業の放射性物質対策研究について説明を受けたという。
ゼロミリシーベルトはあり得ない。正しい知識を全国レベルに
11月初旬、いわき市で開かれた報告会では、こうした経験を踏まえて事故発生から30年超を現地の人々がどのように乗り越えてきたのか、現在の暮らしぶりや同世代の問題意識などを聞き取り、自ら考えたことを参加した高校生一人一人が語った。
報告とパネル討論の2部構成で実施。ベラルーシで受け入れを行った大学生4人も登壇した。パネル討論のコーディネーターはベラルーシ訪問に同行した開沼博・立命館大学准教授・東日本国際大学客員教授が務めた。会場には高校生の家族らも含め約200人が来場した。
参加者の一人は全行程で衛星利用測位システム(GPS)管理が可能な線量計を携行したことに触れた。森の中で線量は少し上がったものの、最も線量が上昇したのは飛行機の中だとの結果を報告。ベラルーシと日本で放射線に対する意識がかなり違うとし、「ゼロ(ミリシーベルト)はあり得ないとの見地に立ち『人体に影響がないレベル』で基準値を設定している」と説明した。
また「これまで学校で放射線についてあまり深く学んでいない」との気付きと共に、「ベラルーシでは子供たちが自分で機材を用いて測定する。日本も専門家による正しい知識を全国レベルで伝えていくことが重要では」などの意見が上がった。
「福島の米を食べてくれ」と胸を張って言い続けたい
「福島の現状を知ってもらうため世界に発信して日本に逆輸入するのも良い」との意見や「農業体験イベントなどはどうか」などのアイデアも出た。コメの全袋検査を継続してほしいと述べた参加者は「費用の問題はあるにせよ『福島のコメを食べてくれ』と胸を張って言い続けたい」との強い思いを伝えた。
パネル討論に特別参加した吉野正芳復興相は「国民一人一人に、正しく放射線を理解してもらうことは国のプロジェクトでも重視している」と説明。風評被害についても「海外の農産物・食品コンクールに出品したり修学旅行の誘致なども積極的に行っている」と述べた上で、「こうして若い世代が真剣に地域や日本の将来を考えていることを大変頼もしく思う」と激励した。
電気新聞2017年11月21日