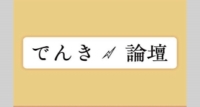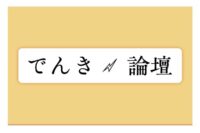◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆
今後のあり方について、最後に2点指摘しておきたい。
まず、今後進展する電源の脱炭素化との関連である。GX推進法で化石燃料賦課金、発電事業に関わる特定事業者負担金が導入されるが、これに先立ち、排出量取引制度が26年度から本格稼働する予定となっている。既に経過措置料金には石油石炭税等の外生的な費用変動を機動的に反映できる制度が手当てされているが、同様に排出量取引等をはじめとして、今後、導入される制度に伴う負担の変化を柔軟に反映できるよう、あらかじめ手当てしておくことが必要と考えている。
2点目は従量料金の3段階逓増料金制のあり方である。1974年に導入された同料金制は、生活必需的な使用量に相当する第1段階の従量料金を比較的低く設定し、これを超過する第2、第3段階の従量料金を逓増させる料金体系で、現在も経過措置料金に組み込まれている。単身・2人世帯が既に全体の66%(20年国勢調査)を占めており、人口構造的に漸増する状況下で、旧一電小売のみならず、これを準用する新電力も3段階逓増料金は徐々に収支を圧迫する要因となっている。特に季節的に電力需要が低下する、いわゆる端境月の収益が使用量以上に低下する影響は大きい。特に新電力にとって月次決算の黒字を安定的に維持することは、資金調達面で重要度が高く、3段階逓増料金制を見直す意義は大きいと考えている。