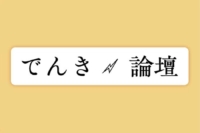◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆
燃料費調整の歴史は古く、1996年に当時の一般電気事業者の料金改定時に全顧客を対象に導入された。本制度では、石油・LNG・石炭の貿易統計価格を火力燃料構成と燃種別熱量比に応じて加重平均することで平均燃料価格の実績値を算出する。この平均燃料価格と料金算定時に同様に算定した基準平均燃料価格との乖離に応じ、小売料金を調整する。本制度の優れた点は単純で透明性が高いことで、導入後、四半世紀余りを経て制度の根幹が維持・継続されている理由は、まさにこの点にある。燃料費調整の上限を料金算定時の基準燃料価格の1.5倍とする扱いは、大幅な燃料価格上昇が顧客に与える影響が大きいことなどを考慮して、制度導入当初から適用され、以来、小売全面自由化後の算定規則にも反映されている。
化石燃料価格はコロナ禍の影響により20年以降低迷していたが、21~22年にかけて、世界経済の動向やロシアのウクライナ侵略等により、原油・LNG・石炭、全ての化石燃料価格が顕著に上昇した。これに伴い電力各社の火力燃料費は急上昇し、22年2月、まず北陸電力の燃料費調整が上限に達した後、同年10月の中部電力ミライズを最後に、全ての旧一電小売の燃料費調整が上限に達した。
このような状況を受け、旧一電小売5社が22年11月末に、同2社が23年1月末に、それぞれ経過措置料金等の変更認可申請を行った。申請の主眼は基準平均燃料価格の改定にあったと考えるが、この時、多くの事業者が燃料費調整の上限制約による収支悪化にとどまらず、これに伴う自己資本の毀損・資金調達環境の悪化の懸念を訴求したのは事態の深刻さを物語っている。その後23年6月1日に料金改定が実施され、基準平均燃料価格も更新されたが、変更認可申請を行った7社の経過措置料金は優に1年前後の長期にわたり、改定前の上限制約を受けていたことになる。なお、残る旧一電小売のうち2社は依然として燃料費調整の上限制約を受けている。
このような経過措置料金の動向が新電力に与えた影響も深刻だった。当時、新電力の多くは旧一電小売の料金体系を準用した上で価格割引を行い、顧客を新たに獲得する営業戦略を採用していた。しかし燃料費調整の上限到達により、新電力にとって最大の競争相手の料金が大幅に抑制されたのである。東京電力エナジーパートナーを例にとると、経過措置料金の燃料費調整単価は22年9月に上限(1キロワット時あたり5.13円、以下同じ)に達したが、その後23年6月に料金改定が実施されるまでの9カ月間、仮に上限がなかった場合の調整単価との差は実に平均5円に及んでいる。
これだけでも新電力の販売にとって十分な打撃といえるが、加えて新電力の主たる電源調達元の1つであった日本卸電力取引所のスポット価格の値付け方式に重要な変化があった。スポット市場の売り入札は余剰電源の限界費用による値付けで実施されてきたが、国際商品市況上昇を受け、電力・ガス取引監視等委員会は21年11月、燃料の追加的な調達価格を考慮し、売り入札を行うことを許容する運用方針を決定した。これを受け複数の発電事業者が売り入札の値付け方針を『調達済み燃料価格』から『追加的燃料調達を考慮した価格』に変更することを表明した。
化石燃料価格の上昇に加え、この値付け方式変更等を背景に、スポット価格は21年度第2四半期(8円)以降、第3四半期(16円)、第4四半期(23円)に顕著に上昇し、22暦年を通じて22円を超える水準(前年は14円)となった。このように販売・調達価格両面で新電力の経営環境は過酷な状況を迎えたのである。