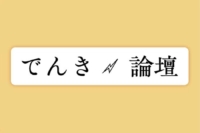◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆
みなし小売電気事業者(以下、旧一電小売)7社は経産大臣の認可を受け、2023年6月に低圧分野の規制料金である「特定小売供給約款」の料金(以下、経過措置料金)改定を実施した。改定の理由は化石燃料価格の高騰による火力燃料費の負担増だったが、その際、問題となったのが「みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則」(以下、算定規則)にある燃料費調整の上限規定である。算定規則には、経過措置料金の燃料費調整は料金算定の前提である基準平均燃料価格の1.5倍を超えることはできないと明記されている。この上限が制約となり、化石燃料価格の高騰を経過措置料金に反映できなくなったため、旧一電小売は料金改定の申請を行ったのである。各社の燃料費調整は22年2月から順次、上限に到達し、値上げが実施されるまでに1年前後を要した。この間、旧一電小売のみならず新電力の経営と低圧分野の顧客獲得・市場シェアに大きな影響を与えた。本稿では以上の経緯が小売電気事業全般に与えた影響を振り返り、燃料費調整の上限を中心に経過措置料金のあり方について考察したい。
日本の小売電力市場では00年3月の特別高圧以降、順次、自由化範囲が拡大、16年4月に家庭用を含む低圧市場が自由化され、全面自由化が実現した。これに伴い料金規制も徐々に範囲が縮小されたが、低圧市場では競争状態が不十分なまま、いわゆる「規制なき独占」に陥ることを防ぐため料金規制を継続する措置がとられた。具体的には旧一電小売に対し、当分の間、経過措置料金等を定め、値上げ時には引き続き経産大臣の認可を必要とすることとなった。
料金規制を撤廃する時期は20年4月とすることを原則としたが、経産大臣が特に指定する旧供給区域の旧一電小売に対しては、その後も料金規制を継続する扱いとなった。同指定は新電力の市場シェアを主とした競争の進展状況等を総合的に勘案し、顧客の利益を保護する必要が特に高いと認められる場合に継続することとされ、現在も全ての旧一電小売が指定を受けている。
指定については継続すべきか、解除すべきか、が議論の中心となってきたが先般の料金改定に至るまでの経緯を踏まえ、継続するとしても、経過措置料金の内容そのものを見直すべきではないかとの意見が強まっている。本来、同料金は自由化後の激変緩和措置で旧一電小売に料金規制を課しつつ、この間に新電力の参入を促進することが必要と考えたために制度化されたものである。以下では、この本旨を踏まえ考察を進めたい。